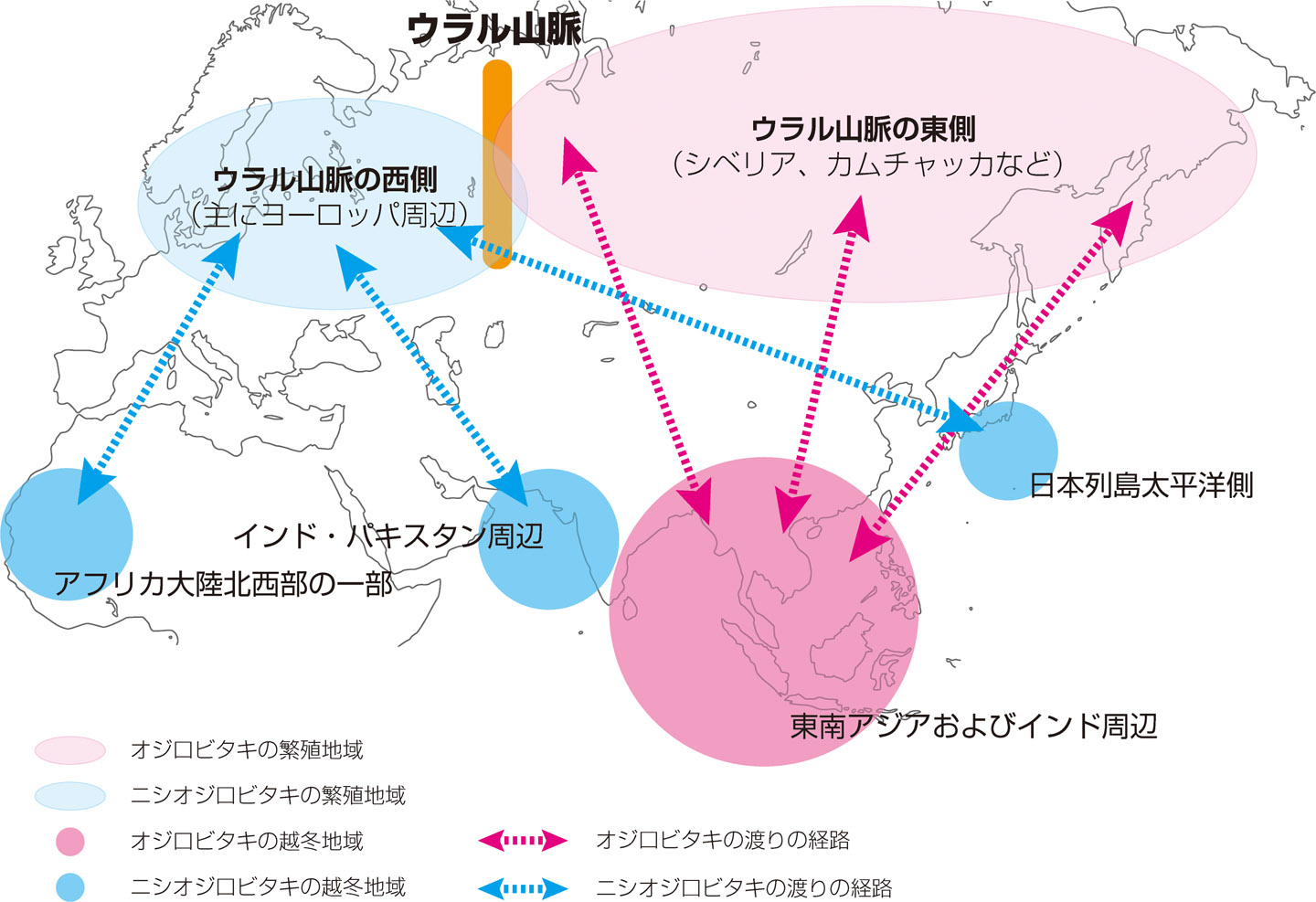城山川のアオバズクについて
Category : 《参考》
アオバズクは、「日本鳥類目録 改訂第7版」(日本鳥学会、2012)では、フクロウ目フクロウ科アオバズク属に分類される鳥類として掲載されています。
学名は、 "Ninox scutulata (Raffles, 1822)、英名は、"Brown Hawk Owl" となります。
夏季、繁殖のため日本列島に渡ってきます。関東周辺では、4月下旬頃からその姿を確認することができます。
営巣中の約53日間(抱卵期間の約25日間+孵化から巣立ちまでの約28日間)は、近隣の公園や神社などの身近な場所で観察が可能となります。
城山川のアオバズクの観察記録
| 年 | 月日 | 概要 |
|---|---|---|
| 2023 | 5/27 | 抱卵開始 |
| 6/19 | 孵化 | |
| 7/7 | 雌が巣穴から出た日 | |
| 7/18 | 巣立ち(1~3羽目) | |
| 7/19 | 巣立ち(4羽目[未確認]) | |
| 2022 | 5/27~28 | 抱卵開始 |
| 6/19~20 | 孵化 | |
| 7/7 | 雌が巣穴から出た日 | |
| 7/21 | 巣立ち(1羽目と2羽目) | |
| 7/22 | 巣立ち(3羽目) | |
| 7/24 | 巣立ち(4羽目) | |
| 2021 | 5/20~25 | 雄が巣からやや遠めの場所にとまり始めた日(抱卵開始) |
| 6/17 | 雄が巣の近くの場所にとまり始めた日(孵化) | |
| 7/5 | 雌が巣穴から出た日 | |
| 7/18 | 19時過ぎに1羽目と2羽目が巣立つ | |
| 7/19 | 19時30分頃に3羽目が巣立つ | |
| 7/20 | 19時00分頃に4羽目が巣立つ | |
| 2020 | 《営巣なし》 | |
| 2019 | 6/8 | 雄が巣の近くの場所にとまり始めた日(孵化) |
| 7/7 | 雌が巣穴から出た日 | |
| 7/19 | 巣立ち(1羽目) | |
| 2018 | 6/25 | 雄が巣の近くの場所にとまり始めた日(孵化) |
| 7/13 | 雌が巣穴から出た日 | |
| 7/24 | 巣立ち(1羽目) | |
| 2017 | 《営巣なし》 | |
| 2016 | 7/15 | 巣立ち |
2023年



2022年


2021年



2019年


2018年


諸々
雌が巣穴から出てから、11日~14日後に1羽目が巣立ちしています。この日数の違いは、雛の羽数によって左右されるような印象です。